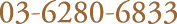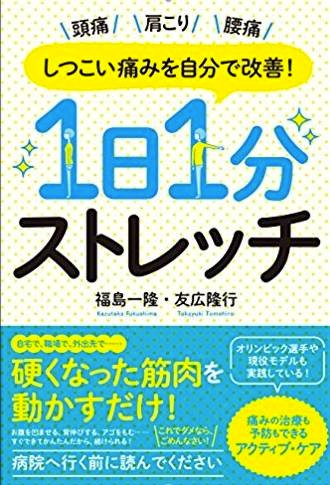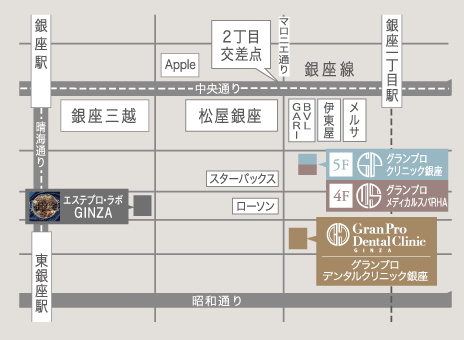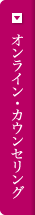自家骨移植
(じかこついしょく)
自家骨移植は、自身の体のある部分から、自分の骨をブロックとして切り取り、ブロックのままか、顆粒状に砕いたあと、骨が足りない部位へ移植する方法です。口腔顎顔面外科では、スタンダードな治療として行なわれてきました。
骨の採取は下顎骨、腸骨(腰)、頭頂骨、脛骨(足)から採取しますが、口腔内の下顎骨からの採取の量は限られた量になりますが、他の部位からは、かなりの量の骨が採取できます。その反面、入院や一時的な歩行障害を伴うこともあります。
ですので、実際の骨移植の場合は、下顎骨のオトガイ部、下顎枝から採取する場合が多いです。採取できる骨の質は、オトガイ部は皮質骨+海綿骨であるのに対し、下顎枝は主に皮質骨となりますので、前者の方がより移植に適していますが、ある一定の割合で、骨採取部位の近くの歯の神経が麻痺などの影響を受けることと、術後に顎の周囲に腫れと内出血を伴いやすいことがあります。後者の下顎枝の場合は、術後の問題は起きにくいです。
インプラント治療の場合ですが、顎骨の水平的な幅、もちくは垂直的な高さが不足している場合、ブロック移植を行います。切り出した自家骨のブロックはトリミングをしてから、骨のない部分(母床)にスクリューで固定します。その後、約4ヶ月、生着まで待機します。サイナスリフトの場合は、顆粒状にしたものを移植します。この場合は、6ヶ月〜12ヶ月待機する場合が多いです。
利点は、自分の骨のみを利用しているという安全に対しての安心感はあります。欠点は、ブロック骨移植の場合、母床骨と適合させるのが非常に難しく、その結果として、血流が不十分になり、移植したブロック骨は著しく吸収してなくなってしまうことがあります。また、サイナスリフトの場合も術後に移植骨がかなり吸収してなくなることがあります。このように、自家骨には、吸収して量が目減りしやすいという欠点がありますが、現在でもスタンダードな術式です。